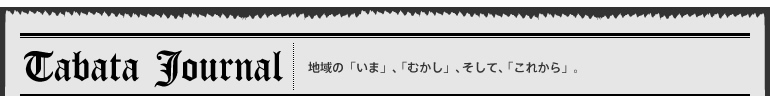『田端文士村を歩く』 第2回:芥川龍之介 「山茶花の塀」


田端駅南口から階段を上がる。細い下り坂を下り、最初の交差路を右手に曲がると、三叉路にあたる。その角の左手が芥川邸の跡地
龍之介の家への想い、芥川家の家への想い
ここが龍ちゃんの家だったんだぜ~。小学校の通学路途中にあった古い万年塀の向こうを指して僕は言った。その日の授業で朗読した「杜子春」の作者が、かつてそこに居たことを誰かに自慢したかった...というのを憶えている。
作家・芥川龍之介が旧田端425番地に移り住んだのは、大正3年の10月。
当時の印象を「学校へは少し近くなった その上前より余程閑静だ(略)ただ厄介なのは田端の停車場へゆくのに可成り急な坂がある事だ(略)だから雨のふるときは足駄で下りるのは大分難渋だ そこで雨の降るときには一寸学校がやすみたくなる」と語っている。
当時の龍之介は、東京帝国大学(現・東京大学)に通う学生だった。下宿というわけではなく、三角の地所に建てられた庭付きの大きな家に養父母と伯母と住みはじめたのである。龍之介は、2階の一部屋を書斎「餓鬼屈」(後澄江堂)とした。
転居した翌年の大正4年、デビュー作「羅生門」を書き、夏目漱石から絶賛され、文壇の寵児となった龍之介の元にはたくさんの人が集まった。雑誌の編集者、先輩や後輩の作家、友人など8畳の書斎はすぐに一杯になった。火鉢の上の鉄瓶が白い湯気を静かに立て、本棚や棚の上、机の周り、壁際の畳の上、至る所に外国の本が、散乱していた。龍之介は二尺の紫檀の机を前にして客をもてなした。話題が豊富で座談が旨い龍之介に客人は誘い込まれて、快談の花が咲き、腰を落ち着けて・・・という具合に忽ち書斎が活気で一杯になった。家の前を通る人々は若者たちの大きな声に耳を向け、二階屋を仰いだ。

芥川家の跡地は、のちに3つに分割され、中央にはアパートも建っているが、コンクリートの壁、それにそって植えられた山茶花の木々は、当時のままに残り、芥川家の息吹を今に伝えている。創作活動に適したであろう閑静な高台の住宅街であることは今も変わらず、俗塵を離れた世界に来たような空気がある
一方、私生活では、この頃から塚本文との縁談が進み始めた。当時の文に宛てた手紙には、「この頃ボクは文ちやんがお菓子なら頭から食べてしまひたい位可愛いい気がします(略)文ちやんがボクを愛してくれるよりか二倍も三倍もボクの方が愛してゐるやうな気がします 何よりも早く一しよになつて仲よく暮らしませう」と熱烈なものを綴っている。
いよいよ大正7年2月、結婚をした。結婚式と披露宴は、田端の白梅園、天然自笑軒で執り行った。芥川家から歩いて数分の料亭である。やがて、比呂志、多加志、也寸志という3人の子供にも恵まれ、公私ともに充実した輝かしい日々を送っていた。
しかし、それから10年も経たない昭和2年7月24日、あの出来事が起こってしまう。龍之介は、「唯ぼんやりした不安」という有名な言葉を残し陰惨な最期を迎えた。心労、神経衰弱、不眠症、睡眠薬の常用、女性関係、創作のいきづまり等、自殺への道程はそろっていた。未遂を繰り返した果てにやっと自殺できたといってもいいだろう。その場所が愛する家族と暮らした、田端の書斎だった。夫の顔を見つめながら文は、「お父さん、よかったですね」とつぶやいたという。愛する家族に看取られながら、息を引き取った龍之介の顔には安堵の表情が浮かんでいた。
龍之介の死後、芥川家は、戦火で追われるまで田端の一角に家を構えていた。生け垣だった芥川家の囲いが万年塀に変わった。さらに塀の外側には、山茶花の木が植えられた。万年塀は、大黒柱を失った芥川家の防犯のためだったのか。山茶花は、味気ないコンクリートをカムフラージュするためだったのか...。
小学生だった僕にとって古い万年塀は、旧芥川邸を示す目印でしかなかった。しかし今は、龍之介と芥川家の気持ちを想う、文士芸術家村の欠片となった。
text by Momen Ittan
illustration by Kazutomo Makabe
photo by Koji Sugawara

profile:一反木綿。1978年生まれ。田端に生まれ、田端に育ち、愛する田端の歴史探索をライフワークとする編集者。文士村の歴史を紐解くことから、地域活性化のためのヒントを探り続けている。只今まちぐるみの文化活動を思案中。滝一小学校、田端中学校卒業生
※ 『田端文士村を歩く』と題したこの連載では、一反木綿さんが田端の魅力を"文士村"という観点から振り返るため、時空を超えた旅に出かけます。田端で活躍した作家、芸術家たちは、当時、田端の地でどんな夢を抱き、どんな暮らしをしていたのか?この旅によって、僕らはこの地にかつて流れていた息吹を感じ取っていきます。そして、この旅を終える時、僕らは願っています。いま以上に田端の町に多彩な人材が集い、多くの交流が行われるためのヒントを得られていることを。田端が文士村と呼ばれた時代のような輝きをもう一度、放つことができるようになるために。
※ 一反木綿さんへの取材のご依頼は、株式会社宅建 担当:阪本幸徳までお問い合わせ下さい。