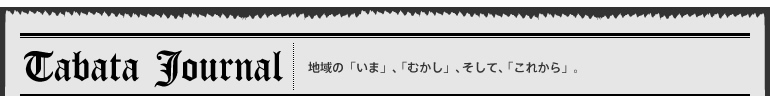『田端文士村を歩く』 第3回:室生犀星 「童橋公園の庭石」


田端駅北口より南側へ続く切り通しの道は昭和8年に完成した。その際に、田端の東西をつなぐ橋としてかけられた童橋。滝野川第一小学校へ通う児童の通学路として利用されていることからか、童橋との名称がついている
亡き児・豹太郎を想い、その俤を庭に見る
おはようございます!元気の良い小学生が黄色い旗をもった古老に挨拶をしている。
滝野川第一小学校の生徒たちの通学路、童橋。その側に、童橋公園がある。この公園には無数の敷石があり、今回はこれが文士芸術家村の"欠片"。詩人・小説家・室生犀星の旧居にかつてあった敷石である。
犀星がその旧居、旧田端523番地(現在の北区田端5-5周辺)に腰を据えたのは、大正10年の3月のこと。生涯の趣味として有名な庭作りを本格的に開始した。石を据え、竹を植え、叡山苔を匍はせ、池を掘ったり、葡萄棚を掛けたり、いろいろと手を入れた犀星は、借家の庭に数寄を凝らしたのだ。
借家に庭を造るほど、犀星は、田端に根を張って居住した作家である。
犀星の親友であり、詩人の萩原朔太郎は、「室生君にとってみれば、田端の風物や環境ほどにも、彼の趣味にぴつたりと合ふものはない。彼の住んでいる景色の中に、丁度彼の「詩」があるのである。室生君と田端の風物とは、最も必然の聯想で結びつけられてゐる。田端の中に室生君が居るのか、室生の中に田端が住むのか、殆ど表象的に分離できないほどである。けだし田端は、室生の郷里金沢と極めてよく類似してゐる。あのお寺臭く、味噌汁臭く、陰気でじめじめした金沢の延長が、丁度田端や根岸辺の風物なのだ。そして此所に、あの俳味や風雅を楽しむ金沢人としての室生が居る」と語っている。
これは犀星が上京以来、田端内を転々とした理由にも重なる。文学史に名を残した雑誌「感情」を発行した駆け出しの頃は、百姓家の下宿宿。結婚後に住んだ、玄関二畳に縁側つきの六畳、四畳半と台所、南に十坪ほどの庭がつき、手広くなった平屋の二軒長屋。そして、子どもが生まれ、玄関2畳、書斎8畳、茶の間6畳、納戸3畳のおよそ60坪の「家族の城」がようやく形作られた。

童橋公園内には室生犀星の旧居にあった庭石を現在でも見ることができる。昭和3年、犀星が大田区馬込ヘ転居する際、隣家に住む広瀬雄がこの庭石を引き取った。 その後、広瀬雄の子息が公園設置の記念に東 京都北区に寄贈した。「叡山苔」という苔も一緒に寄贈されたが、環境に合わず、童橋公園では見ることができない。ただし、広瀬雄の旧居及び北区王子の名主の滝公園では犀星の育てていた苔を見ることができる
詩人・小説家として認められ、仕事が充実し、私生活でも結婚、子供にも恵まれ、輝かしい日々を送っていた犀星。しかし、長男・豹太郎が生後まもなくこの世を去ってしまう。
犀星は亡き児・豹太郎を哀れみ、その俤を庭にみている。亡き児の通う径への心遣りまでに「冷たい動かぬ飛び石をうつ」といっている。犀星は庭の広がりを湖にみたて、お盆には迎え火を焚き、豹太郎や亡くなった友人の霊を弔って、「みんながこの石を伝って会ひにくる、みんな水際を歩いてくる、古い時間が流れる」と付け加えた。
童橋公園の敷石はただの石ではなく、犀星の亡き児への想いがこめられ、そして犀星の田端時代を語る上でかけがえのない文士芸術家の"欠片"となった。
text by Momen Ittan
illustration by Kazutomo Makabe
photo by Koji Sugawara

profile:一反木綿。1978年生まれ。田端に生まれ、田端に育ち、愛する田端の歴史探索をライフワークとする編集者。文士村の歴史を紐解くことから、地域活性化のためのヒントを探り続けている。只今まちぐるみの文化活動を思案中。滝一小学校、田端中学校卒業生
※ 『田端文士村を歩く』と題したこの連載では、一反木綿さんが田端の魅力を"文士村"という観点から振り返るため、時空を超えた旅に出かけます。田端で活躍した作家、芸術家たちは、当時、田端の地でどんな夢を抱き、どんな暮らしをしていたのか?この旅によって、僕らはこの地にかつて流れていた息吹を感じ取っていきます。そして、この旅を終える時、僕らは願っています。いま以上に田端の町に多彩な人材が集い、多くの交流が行われるためのヒントを得られていることを。田端が文士村と呼ばれた時代のような輝きをもう一度、放つことができるようになるために。
※ 一反木綿さんへの取材のご依頼は、株式会社宅建 担当:阪本幸徳までお問い合わせ下さい。